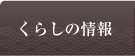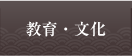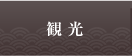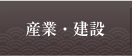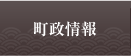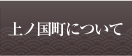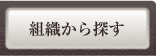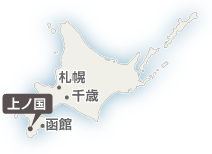会議は決める場でなければならない
2024年10月21日
先日、ある産業団体の検討委員会に委員として出席いたしました。内容は、団体の存亡に不安要素があるので、その対応策について検討するというのが開催趣旨であります。
最初、団体がおかれている現状の課題と、今後予想される課題についても事務局より説明がありました。
どの課題も一朝一夕で解決できるようなものでないと理解しましたので、この解決に向けては、手術に喩えると、ある程度の出血も覚悟しなければならないと思って会議の進行を見守っておりました。
当然ながら、各検討委員からは相当辛辣な意見も出されました。
それでも、団体の行く末を思っての意見なので、もっともだろうと思って拝聴しておりました。
そして最後、意見も言い尽くされたということで今後の検討案が事務局より提案されました。
内容は、課題解決に向けて、各事項について今後“検討していく”という趣旨でありました。
私とすれば、あれほど辛辣な意見が出されたので、“検討していく”などとぬるま湯的な案はダメだという声が挙がるだろうと予想しておりました。
ところが、各委員あまりにも大きな課題だと自覚していたこともあったと推測されますが、何の解決策も示されない検討案が承認される雰囲気になってしまったので、異を唱えました。
私の意見は、“検討”という字句を削除し、今まで無理だろうと思われた方策も含めて具体策を明示しようということです。
最終的に私の意見がとりあげられ、もう一度再考しようという結論に至りましたが、ある本で読んだ日本社会で行われている会議のことを思い浮かべました。
著者曰く
日本の会社は、総じて判断が遅い。
何かを決めるために会議を開いても簡単には結論を出せず、「引き続き慎重に検討しよう」「しばらく様子を見るべきだ」などと言って、最終的な判断を先送りすることが多い。
会議は本来「決める場」なのに、「話し合う場」になっている。
まさに、的を射た指摘であります。