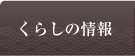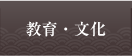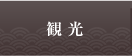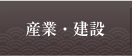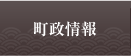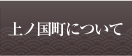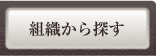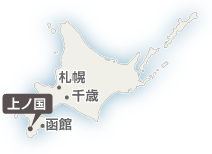古典を拠り所として
2006年12月13日
私は、若い職員に古典を勉強するよう促しておりますが、ある時「何故、今更古典なの?」と職員から質問されたので、次のような経験談を話しました。実は、私も若い頃は古典は古くさいと思っておりましたが、日本の一流企業トップの本を読むと、必ずや古典のお話が随所に出てきます。
それも、トップとして何らかの結論を出さざるを得ない時、古典を拠り所としております。
古典と言えば、孔子、孟子、老子、荘子等々が挙げられますが、この中国思想の大家は今から2千年前の人たちばかりであります。
その当時は、地球が丸いことも、水は酸素と水素でできていることも知らない無知な時代であります。
翻って今は、原子力も作れるし、月に行って帰ってくることもできる時代となりました。
しかし、どんなに科学や文明が発達しても、私たちは鳥のように空を飛べません。
また、魚のように水の中に住むこともできません。
鳥や魚のようになるには、機械の力が必要であり全て他力であります。
そう考えると、人間としての根源的な感情や能力等は変わっておりません。
昔の方が、文明が発達していない分だけ感情を統御していたとも言えます。
そのようなことから、たとえ何千年前の人間であっても尊敬でき、師匠として仰ぎ見ることもできると確信しております。
特に町長となってから、古典は生活の一部であります。
私が古典を拠り所とした例として、課統合の決断がありました。
課の統合は、将来を見越して12課を4課に統合するわけであります。
統合することにより、12人の課長は4人となり、他の8人は参事か室長となります。
待遇は同じだとしても、参事か室長だと何となく格下げになったような気がするものです。
課長会議では、当然のごとく反対論が出ました。
「何故、今うまくいっているのに変えなければならないのか?」「必要になった時に、変えてもいいのではないのか?」等々であります。
正直、私も悩みました。
急いで改革をしなくてもいいのではないのかという思いも心のどこかにありましたが、私は、大きな決断をする際は必ず古典をひもときます。
その時も古典に活路を求め本を読んでいたら、“任怨”(にんえん)という言葉に出会いました。
“任怨”とは、要職にある者が、大事を断行しようとする場合、どうしても恨みというものは免れない。必ず誰かが恨み、どこからか恨まれる。それを恐れていたのでは何もできない。だから甘んじてその恨みに任じる者でなければ、到底要職の資格がないと言う意味であります。
トップにとって決断は避けて通れないことでありますが、誰しもいい人になりたいし、波風も立たせたくありません。
しかし、トップは、非情にならなければなりません。
それがいやだったらトップにならないことであります。
この言葉で、私の腹は決まり課の統合を断行いたしました。
このようなことから、私にとって古典は人生を諭してくれる偉大な師匠であります。