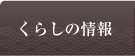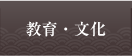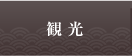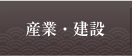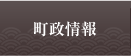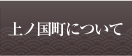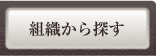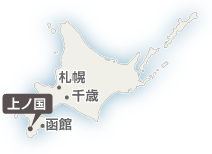昭和の時代に置き忘れてきたもの
2005年8月29日
町の施設である旧笹浪家には、昭和の時代使用していた調度品がたくさん展示してあります。中でも、台所用品の「水瓶」とご飯を炊く「つば釜」にはたいへん懐かしさを覚えます。
水瓶。
水道のない時代には、台所に必ず水を貯めておく水瓶がありました。
飲み水は、瓶から柄杓で汲んで飲むわけでありますが、寒い冬の朝などは瓶の中に薄氷が張っておりました。
梅雨時は、ナメクジが入っていたりしました。
そのナメクジを手で捕ったあとその水を飲むわけでありますから、あまり良い気持ちはしませんでした。
それでも、お腹を痛めたりアトピーになったりという話も聞きませんでした。
つば釜。
今は炊飯ジャーで、誰でも美味しくご飯を炊くことができますが、昔は鍋の回りにつばのついた「つば釜」で炊きます。
つば釜で炊くと、本当に美味しく炊けます。
また、ご飯を炊いた釜の内側下に茶色くご飯がこびりつきますが、それがまた食べると美味しくて、よくおにぎりにして食べたものであります。
しかし、電気炊飯ジャーではこびりつきがないため、食べたくても食べることができません。
旧笹浪家には、このほかにも板敷きの床や炉縁等を復元しておりますが、そこにいると40年前にタイムスリップします。
今は、昭和の時代と比べものにならないくらい便利な社会になりました。
しかし、便利になった代償として、昭和の時代へ何かを置き忘れてきたと感じるのは私だけでしょうか。