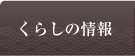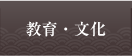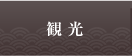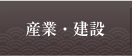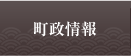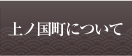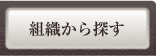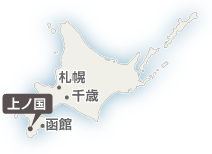「結いっこ」に思う
2002年10月30日
結いっこ。子供の頃は毎日のように聞いていたが、今では、私たちより下の年代は意味合いも知らないと思われます。
学問的な意味はわかりませんが、お互い承諾の上で、お手伝いの貸し借りをするという解釈でしょうか。
英語のギブ・アンド・テイクとは違い、お互いが助け合うという暖かみが感じられます。
昨今、農家にはトラクターやコンバイン等が導入されたため、農作業での隣近所のお手伝いも必要でなくなってきたため、農家特有の「結いっこ」も聞かれなくなってきました。
そういえば、この頃より盆踊りや町民運動会などの、田舎特有のコミュニケーションの場への参加が少なくなってきたように感じられます。
それは、人と人との心を交わす場がなくなってきたのが大きな要因であり、「結いっこ」は思いやりという副産物を醸成していたのではないでしょうか。
他人事と思っていた都会での「心の砂漠化」が、だんだん田舎にも広がってきており、人口の過疎化と心の過疎化が同時進行しているように見受けられます。
今ここで危機感をもってくい止めなければ、「結いっこ」という言葉ばかりでなく、ふるさと上ノ国の良さも見失ってしまうのではないでしょうか。
完璧な対応策はないかもしれませんが、その一つとして、町内で開催する各種行事に積極的に町民が参加・協力するような、現代版「結いっこ」を提唱いたします。