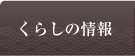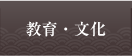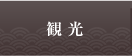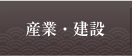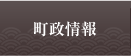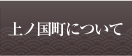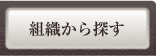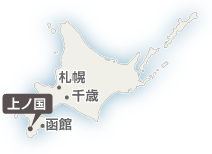昔懐かしい“スズメ追い”
2007年10月15日
先日、敬老会に出席したときのことです。乾杯も終わり話題が米の作況となったときに、隣に座っていたお年寄りから「そう言えば、町長は、小学生の頃いつも“スズメ追い”をしていたなあ。遊びたい年頃だったのになあ」と言われましたが、同行していた若い職員は、話の意味がわからなかったようなので説明いたしました。
私たちが小学生の頃は、稲の刈り取り時期になると、スズメが集団で稲の穂を食べに田んぼに来るため、そのスズメを追い払うことが子どもの役目でありました。
追い払う方法として、田んぼの端から端までに何本かの杭を打ち、その杭と杭の間に長いヒモを這わせ、途中何カ所かに空き缶をまとめてぶら下げておきます。
そして、ヒモの一端を引くと空き缶どうしがぶつかり合って、何カ所もの空き缶がカランカランと鳴るので、スズメがビックリして逃げていくという仕組みであります。
このように、ただ単にヒモを引っ張るだけなので、もっぱら子どもの役目でありました。
ところが、ムシロの上で黙って座ってスズメを待っているだけなので、時々眠ってしまうこともあります。
そのため、何冊ものマンガ本を持っていき読んでおりました。
平日は、当然、学校を休んで“スズメ追い”をするわけでありますが、小学生が農家仕事で学校を休むなんて、今では考えられないことかも知れません。
今から、約40年前の懐かしい思い出であります。