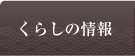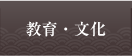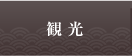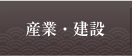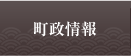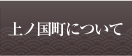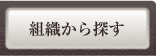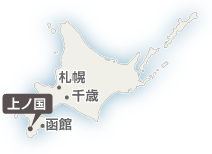漁業者の「心おこし」を期待して
2013年2月8日
明治大学齋藤孝教授のエッセイの一節です。小学生の頃、小学校のプールに一学年6クラスの生徒全員が入って、運動場を回るように、同じ方向にグルグル円を描くようにして歩いた。
しばらく歩いていると水流が起こり、“凄いスピード”の流れるプールができあがった。
歩き続けているうちに水に勢いが出て、その勢いがどんどん強くなっていく。
そのうちに水に背中を押されるようになり、歩くのが楽になる。
なかには、水流に体を預けてプカプカ浮いてはしゃいでいる子もいたが、真面目な子はずっと歩き続けた。
私は最近、社会というものは、この“流れるプール”みたいなものなのではないのかと考えるようになった。
社会が円満に回っていくためには、みんなが一所懸命に学び、真面目に働き続けなければならない。
その歩みを止めると、やがて社会の勢いが弱まり、停滞してしまう。
ちょうど「今の日本」は、そういう状態にあるのではないか。
「今の日本」を、「今の上ノ国」に置き換えることができます。
要は、町の流れを変えるのは町民一人ひとりが歩き続けることです。行政はただ、それを補完することだけより出来ません。
例として、漁業の活性化を図るとしても、水産課の職員が漁に出るわけではありません。
主役はあくまでも漁業者です。
しかし、長年、不漁が続いてしまうとその自覚も薄れてしまい、漁業者自らが、小学生のように歩き続けることを躊躇しているように思えてなりません。
そのことから、今月25日上ノ国町の漁業者を参集しての「上ノ国町漁業大会」を開催いたします。
本大会は、初めての開催です。
目的は、漁業者一人ひとりの「心おこし」であり、漁業者自らが水流を起こすきっかけになればと期待しております。