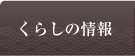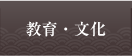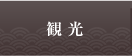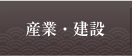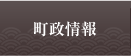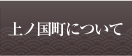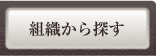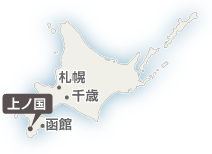米百俵の精神
2006年7月14日
米百俵の逸話は、小泉首相が取り上げて一時有名になりました。内容は、戊辰戦争で焦土と化した城下町の長岡藩(現在の新潟県長岡市)に、窮状を見かねた親戚筋の三根山藩より見舞いの米百俵が届けられた話であります。
三根山藩より米百俵が届けられたことを聞き、配分を心待ちする藩士が手にしたのは「米を売り学校を建てる」との通達でありました。久しぶりに白米を食べられると楽しみにしていた藩士は怒りだし、病弱の大参事小林虎三郎の横たわる畳に白刃の刀を突きつけ、米を要求しました。学校などどうでもいい。学問など役にも立たない、と。
その時小林虎三郎は、「長岡藩には千七百世帯、八千五百人の家族がおり、米を分けても一日か二日で食いつぶして終わりだ。長岡を立て直すには人物が必要だ。全ては人だ。子どもに託すしか方法はない。畳に突きつけられた白刃の刀をよく見ることだ。刀は、偉大な師匠である。長岡の再興に何が一番大事か。土台となる大本を定めることだ。見舞いの米などこなかったと思えばそれですむ。今大事なのは、ただの百俵を後年に一万俵、百万俵にすることであり、それが三根藩への恩返しでもある。国の充実には学問が必要だ。学問を興し、心を一つにして人をつくることだ。」と説きました。
その甲斐あって、長岡藩からは明治政府の要人がたくさん輩出されております。
今、本町の建設業者は、工事量が極端に少なくなったことから危機的状況にあります。
必然的に、町内での雇用も控えざるを得ません。ある社長は、来年あたりから働く場がない町民が町を出て行き、過疎が助長されるのではないかと危惧しておりました。当然のごとく、町に対し工事量を増やしてくれるよう要望してきます。
しかしながら、実情を理解したとしても本町の財政状況を勘案すると、工事発注を増やすことはせいぜい二~三年が限度であります。小林虎三郎曰わく、米を分けても一日か二日で食いつぶしてしまうのと同じこととなります。
建設業にも、米百俵の精神を活かすことができないものかと感じた次第であります。