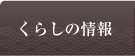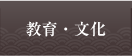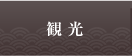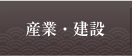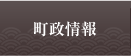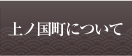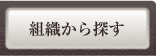「お世話です」の一言が。
2012年8月1日
ある雑誌に載っておりました。私自身、魂を揺さぶられましたのでご紹介します。
「お世話様です」
その言葉は私の胸へ静かに沁みわたった。
東日本大震災の発生翌日から、遠隔地の警察官ながら宮城県石巻市へ派遣された私にとって、東北弁独特の言い回しで物哀しささえ残るその言葉は、その時の私が置かれた状況とあいまって、時に強く訴えるものがあった。
ご遺体を安置所に運び込む
出発前、「一人でも多く被災者を助けるぞ!」固く心に誓って現地入りした私達の行く手に立ちふさがったのは、怪物のような瓦礫の山と何十、何百という老若男女のご遺体だった。バール一本で瓦礫と格闘しながら海岸や家屋の中でご遺体を発見しては安置所に運び込む毎日を送ることになり、死因を特定する検死が終わるのを待って納棺し、線香と花を手向けて合掌する日が続いた。そして、必然的なことだが、ご遺体の数だけ遺族がおられた。
現地ではあまりのご遺体の多さに葬儀業者も手が回らず、遺族が高齢者の場合で運べない時には私達が車まで棺を運んだ。ドライアイスでの保存が効かなくなれば指定の場所に穴を堀り、仮埋葬して番号だけの墓標を立てるなど、初めて経験する任務となった。
派遣が終わり、元の職場に戻った時、その任務内容を聞いた同僚達は、「そんなことまで!何でそこまで!」と驚いた。上層部に至っては、「遺体に長く触れると感染症になるじゃないか!」という者までいた。連日のように安置所で号泣される遺族の悲鳴を耳にし、あの悲惨で哀しみの極致に居合わせなかった者が言う資格はない。しかし、私がどれほど言葉を尽くしてみてもその哀しみは伝わらなかった。私達が現地で行なったことは任務ではない。人間としての使命感だったのだ。そして、そんな時に必ず遺族の口から聞かれた言葉が「お世話様です」という言葉だった。普段、私達が耳にする「ご苦労様です」「お疲れ様です」という儀礼的なものではなく、冒頭に記したように、東北派遣中は至る所でこの「お世話様です」を聞いた。この言葉を聞くたびに私の胸は張り裂けそうな感覚が支配した。
きっと、最初に決意した「必ず被災者を助けるぞ」という意気込みが現実の厳しさを前に挫折して、諦観にも似た感情に移っていったからだろう。大津波や地震で犠牲となられた方や遺族から私達は「お世話様です」と言われる立場にあるのか、という忸怩たる思いがそこにはあった。だがその中で最も哀切極まる、私を支えてくれた「お世話様です」を言ってくれた人がいた。
魂を揺さぶった幼児の一言
あれは何体目に搬送したご遺体だっただろう。長い髪の若い女性だった。津波に襲われたその女性は、衣服のポケットにあった診察券から身元が判明し、遺族であるご主人と幼稚園児の娘さんが安置所で対面された。号泣されるご主人の横でただ寄り添い、たたずむことしかできない私だった。パパの傍らで、棺の中に横たわるママの顔を覗き込むお嬢ちゃんは、しきりにママへ囁いた。
「ママ。ママ。起きて。帰ろう。ね?」そう無邪気な声で囁いた。ママは今すぐに起きあがるのでは、と思うほど綺麗な顔をしていた。私にとって長い長いご遺体確認の時間が終わり、明日引き取りに来る二人を出口まで見送った時だった。「お世話様です」と頭を下げられたパパと繋いでいた手を離し、お嬢ちゃんは気をつけの姿勢となって、「おまわりさん。お世話様です」そう言ってペコリとお辞儀をしたのだ。一瞬、その子の顔が家で待つ自分の娘の顔と重なった。突然、ぐっと迫ってきた涙をようやくこらえ、私はしゃがみ込んで、お嬢ちゃんの頭に手を置いて撫でてあげた。そうしなければ、私はきっと耐えられなかっただろう。「えらいね。こちらこそ。お世話様です」泣き笑いの顔だったけれど何とか言えた。お嬢ちゃんは嬉しそうな顔をして私に向かってバイバイし、何度も振り返っては頭を下げられるパパと一緒に帰って行った。
*
東北への長い派遣を終えて元の生活に戻った今、仕事先から帰る途中に夜空を見上げることが多くなった。澄み切っていた星を見上げながら思う。あの子のママもあの星のどれかになって、あの子をずっと守り続けてほしい。そして最後にこうつぶやく。「お世話様です」。
戦後に対比される災後という言葉までが生まれた東日本大震災。我が国未曾有の困難に際し、被災地で多くの犠牲者の死と残された遺族の生を間近で見て、歯を食いしばりながら野辺の送りに寄り添った。そして固く誓った。この事実を語り継ぐことを。それがせめてもの手向けになるのだと信じて。
「お世話様です」。私を支え、魂を揺さぶった言葉である